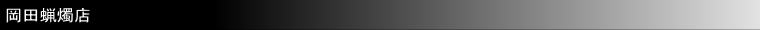|
蝋燭はその本体と芯の2つで形成されています。


 |
| パラフィンワックス板状 |
今日、一般的に市販されている蝋燭やキャンドルの原料として使用されています。
パラフィンワックスは原油中に存在する常温において固体または半固体の炭化水素になります。
1854年頃にはすでにパラフィンワックスを使用したろうそくがイギリスで作られました。価格が安
く、型でも作りやすいので大量生産されスーパーや量販店でよく見かける蝋燭です。

うるし科の木であるはぜの実から抽出した蝋分です。
豆のような実で、中心の果肉と外皮との間の薄皮から一番蝋分が採れるそうです。
はぜの木は南の九州や四国などの暖かい地方に多く自生している植物で、逆に北の方では漆
の木があったため漆の副産物として昔は漆の実からも蝋を採り、その漆蝋を使って和蝋燭を作っ
ていました。最近では会津の方で復活したとの話を聞きますが、当店でははぜ蝋を使用します。
代表的なものに伊吉、昭和福、葡萄、松山はぜなどがあります。
種類により色や硬さが違い、下地を作る生蝋は茶色であり、仕上げに使う上掛け蝋は葡萄はぜ
が多く含まれていて緑色をしています。また白蝋は生蝋を天日に晒し自然に漂白したものです。

 |
| ぬか蝋 |
米ぬかから抽出し融点が高い蝋です。
写真のぬか蝋は脱色していないものです。
脱色したものはクリーム色をしています。

ミツバチの巣から採れる蝋です。ミツバチは自分の体に蝋腺をもっており、巣に蜜を貯める際一杯
になった蜜がこぼれないようふたをします。その時、蝋腺から蝋を出しそれでふたをします。蜂蜜
を採取する際にとれます。原料としては一番古くからあるそうです。
日本に最初に入ってきた蝋燭も蜜蝋を使用したものと言われています。
自然のものは、ほのかな蜜の香りがし綺麗な明かりでが、市販されているもので香りの強いもの
は香料が入っていることが多いようです。


綿糸を編んで作ったもので、キャンドルや和蝋燭にも今日においては一般的に使用される芯で
す。蝋燭の太さや硬さに合わせ心の太さを変えます。
パラフィンワックスや蜜蝋を原料とした蝋燭に使用されることが多く、均一に編んであるため安定
した炎になります。また燃焼するに連れ芯が丸まるため温度の高い炎の外側で燃焼され芯きり
が必要ありません。ただし炎が小さいため屋外では風に消えやすいです。

 |
| 紙芯 |
筒状に巻いた和紙の上に柔らかいちり紙などをまいたもので、和蝋燭によく使われます。和蝋燭
の原料がはぜ蝋からパラフィンワックスに変わり、灯心を使わなくとも燃焼がいいためその代替
品として使われるようになったようです。ロウの吸い上げが多く炎が大きめになります。風にも消
えにくいのでお墓参りや屋外で使用したり、大きな炎を必要とする時に使用します。

筒状に巻いた和紙の上に灯心を巻いたものです。イグサの種類で外皮を裂きその中から引き抜
いたズイの部分を灯心といいます。スポンジの様な素材で1m程の長さがあります。切れやすく
巻くのにも慣れが必要です。昔は灯明皿に菜種油を入れそこに灯心を浸し火を点け明かりを取っ
たりしていました。はぜ蝋を原料とした蝋燭では糸芯でも紙芯でも吸い上げが悪くきれいに燃え
ません。
今でもはぜ蝋で蝋燭を作る時は灯心を使用します。灯心は植物のズイを利用した自然素材なた
め一本一本太さが違い、それを手で巻いていくためどうしても場所により芯の厚さが違ってきま
す。それによって和蝋燭の炎が安定せず、瞬きのある炎になると思われます。そういった表情の
ある和蝋燭の明かりは今日の安定した明かりのある生活の中では、逆に心を落ち着かせてくれ
ると思います。
和蝋燭の明かりが照らす空間は広くはないですが、その空間は普段のものとは異なり、特別な
時間を過ごせる空間となります。
|